「うちの子、ちゃんと勉強してるのに、なかなか成績が上がらなくて…」
こんな声を、保護者の方からよく聞きます。
実は、「勉強している=効果的な勉強ができている」とは限らないのです。
今回は、塾講師として数多くの生徒を見てきた中で見えてきた、**成績が伸びにくい子に共通する「問題集のやり方」**をご紹介します。
もしかすると、お子さんにも思い当たる点があるかもしれません。
① 複数ページをまとめて丸付けしている
やりがちですが、これは危険な習慣です。
解いてから丸付けまでに時間が空くと、「なぜ間違えたのか」が分からなくなります。
記憶が新しいうちにすぐ丸付け → 間違いを確認 → 覚え直し、の流れが成績アップの鍵です。
② 解説を読まず、理解しないまま答えを写して終わり
「できた風」になってしまうパターンです。
わからなかった問題を答えだけ写して終わりにすると、知識として定着しません。
特に数学や理科では、「なぜそうなるのか」を理解することが何より大切です。
本人が嫌がらなければ保護者の方が、「どうしてその答えになるの?」と声をかけてみてください。
③ 間違えた問題に印をつけていない
「できなかった問題」が分からなくなると、復習のしようがありません。
・×をつける
・付箋を貼る
・ページの角を折る
など、自分の苦手を残す工夫が必要です。
④ 印がついた問題を解きなおしていない
間違いに印をつけても、解きなおさなければ意味がありません。
一度間違えた問題を“もう一度”やることで、脳が「これは大事!」と認識し、定着度がぐんと上がるのです。
間違えた問題こそ、自分に必要な「伸びしろ」です。
⑤ 問題を「自分の言葉で説明する」練習をしていない
これは意外と見落とされがちですが、最も効果のある勉強法のひとつです。
誰かに説明できるということは、「理解している証拠」。
音読でも、ノートへの書き出しでもOKです。
たとえ相手がいなくても「これはこういう理由でこうなるんだよ」と独り言でも自分の言葉で再現する練習ができている子は、成績の伸び方が違います。
おわりに:大切なのは“正しいやり方”を身につけること
問題集は、ただこなすだけでは成績は伸びません。
どんなに時間をかけても、「やり方」が間違っていれば、結果はついてきません。
お子さんの「問題集の使い方」、ぜひ一度見直してみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
こんな感じで、毎週木曜日9時に投稿を続けていっています。
次週は『【幼児教育】絵本の読み聞かせが学力に与える驚きの効果とは?』をお届けしますので楽しみに待っていてください。
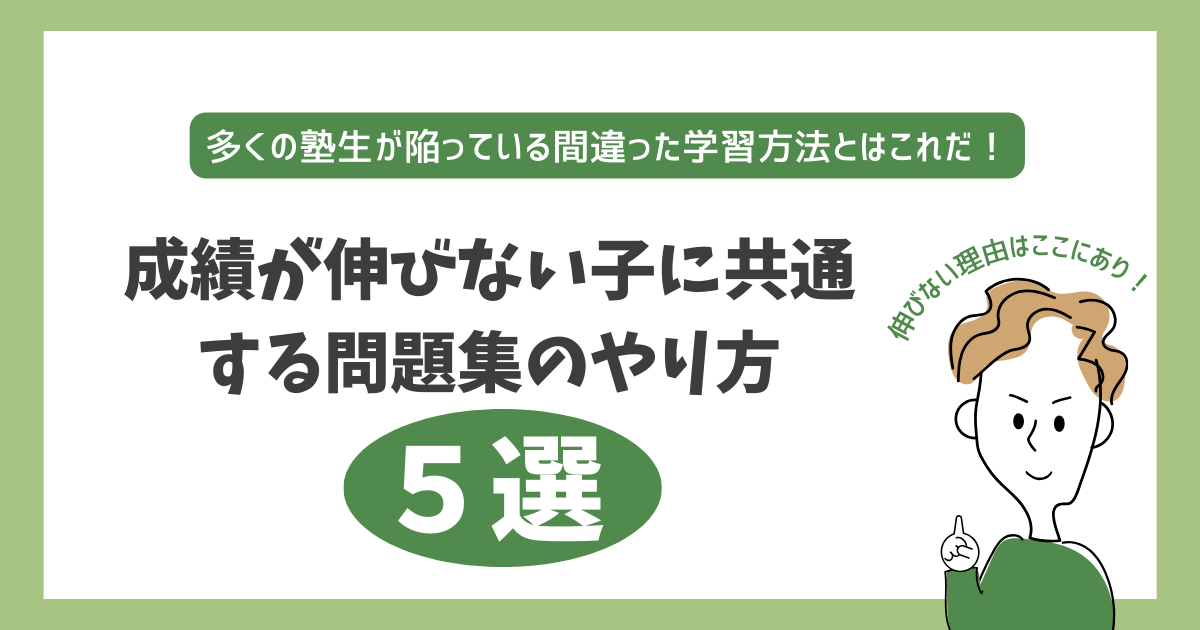
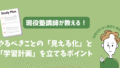
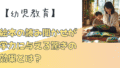
コメント