学期末になると学校から渡される「通知表(あゆみ)」。
子どもの学習状況や学校生活の様子を知る大切な資料ですが、数字や評価ばかりに目が行ってしまい、子どもを責める言葉をかけてしまう…という経験はありませんか?
今回は、通知表の見方と声かけのポイントを整理してみます。
1. 通知表は「成績表」だけではない
通知表は単なる成績の一覧ではなく、子どもの成長を多面的に映し出すものです。
教科の評価に加え、生活面・態度・努力の記録なども含まれていることが多く、学力だけでなく「取り組む姿勢」や「学校での人間関係」も読み取ることができます。
数字や◎○△の評価だけでなく、担任の先生のコメント欄にしっかり目を通すことが大切です。そこには子どもの小さな成長や努力の跡が書かれていることが多いのです。
2. 見るときの基本姿勢は「成長探し」
通知表を見るときに最初に意識したいのは「できたことを探す」視点です。
人間はつい不足や課題に目が行きがちですが、子どもにとって一番大切なのは「努力を認められた」「成長していると感じられる」こと。
例えば、
- 「前よりも○○の評価が上がっているね!」
- 「生活面のコメントに“友達を助けていた”って書いてあるね。素敵だね」
といった具合に、評価の変化やコメントから子どもの良い点を具体的に伝えましょう。
3. 改善点を伝えるときの工夫
もちろん課題や弱点にも目を向ける必要はあります。ただし伝え方が大切です。
- 「ここがダメだったね」ではなく → 「ここは次に伸ばせるチャンスだね」
- 「もっと頑張りなさい」ではなく → 「どうすればうまくいくと思う?」
といったように、子どもが次の行動につなげられる言葉を意識しましょう。
親からの一方的な指摘ではなく、子どもと一緒に考える「対話型の声かけ」が効果的です。
4. 声かけの具体例
- 「頑張ったところを一緒に見つけよう」
- 「どんな工夫をしたらうまくいったの?」
- 「次はどんなことに挑戦してみたい?」
このように、振り返りと次の目標を子ども自身の言葉で語らせることで、主体的な学びにつながります。
まとめ
通知表(あゆみ)は、子どもの「点数」や「順位」を判断するためだけのものではなく、成長の記録です。
良いところをまず認め、そのうえで課題を一緒に考えていく姿勢が、子どものやる気を引き出します。
ぜひ次の学期に向けて、前向きな会話のきっかけにしてみてください。
✅ 最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
こんな感じで、毎週木曜日9時に投稿を続けていっています。
次週は『小学生から始めるノートの取り方・復習の習慣化』をお届けしますので楽しみに待っていてください。

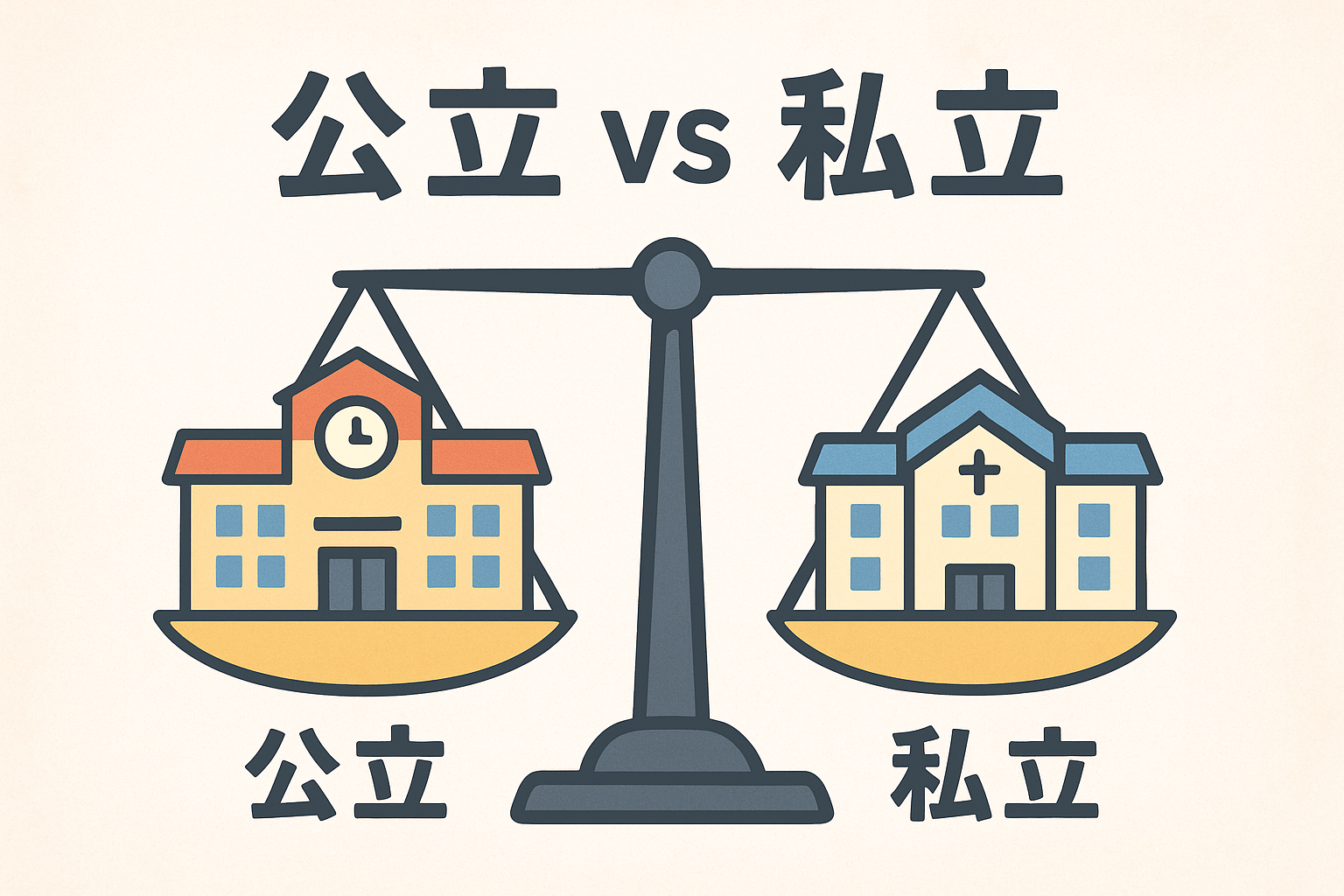
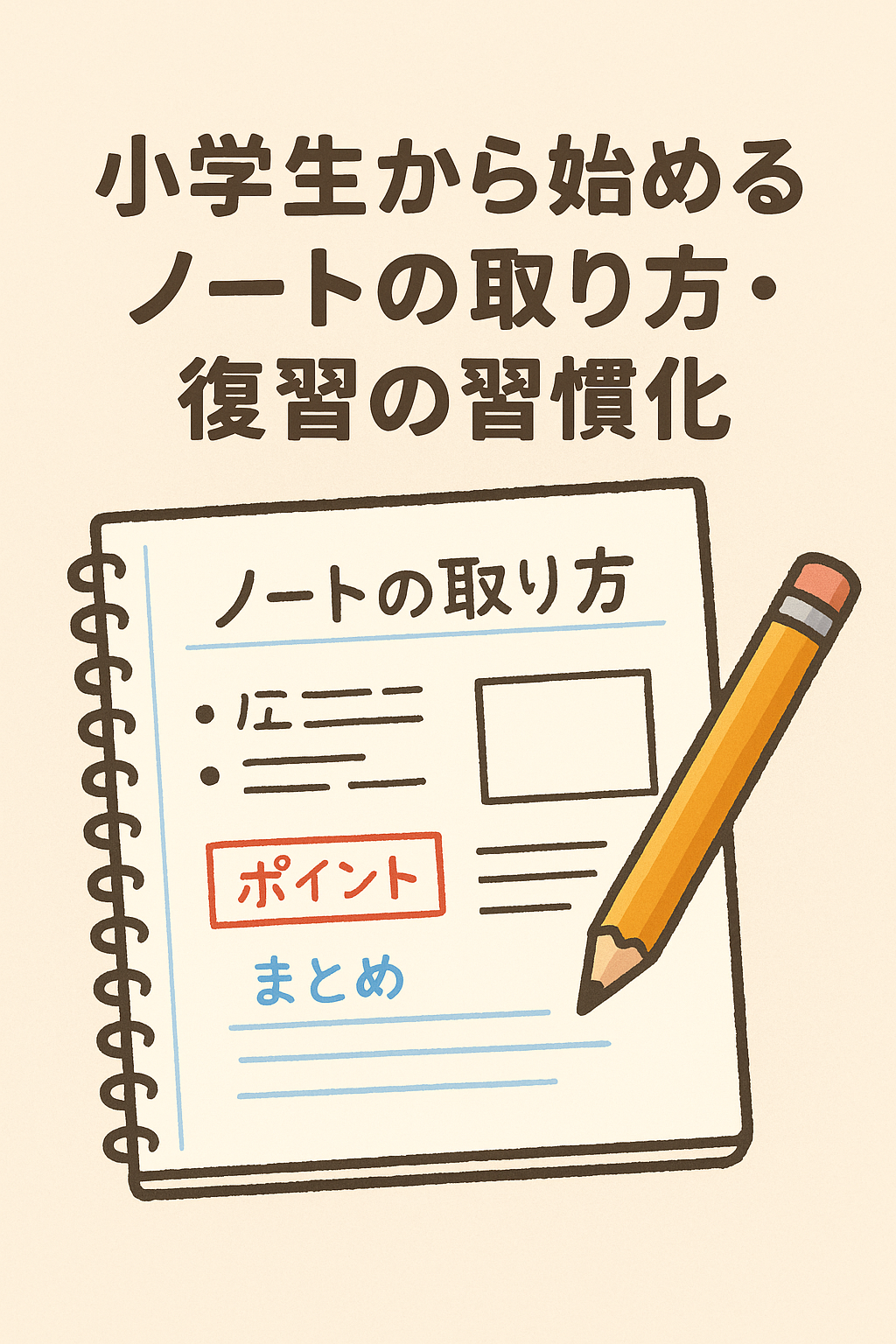
コメント